|
Domaine de l'Ecu 〜土壌別にミュスカデを飲んでみる〜 (La Bretonnière 2004.11.17) |
ドメーヌ・ド・レキュは、ミュスカデで評価が最も高いドメーヌの一つである。私も何度かこのドメーヌのワインは口にする機会があったが、純度の高いミネラルと新鮮な柑橘のニュアンスは「ああ、レモンをぎゅっと搾った小振りの牡蠣を食べたいっ!」という食欲をダイレクトに誘い出すもので、ミュスカデのかわいそうな評価「ピピ・ド・シャ(猫の小便臭)」などは、微塵も無い。
ミュスカデはフランスでも高価なイメージとはほど遠いが、とにかくこのドメーヌのミュスカデは「アペラシオン名でワインを判断してはいけない」ワインの典型である。そして今回の訪問で理解したことは、その仕事ぶりも「このアペラシオンでは別格」で、しかし購入したワインはカーヴでの購入価格とは言え、最高で5ユーロ台。ミュスカデという名ゆえにこの価格が付けられているのなら、それは間違いである気すらしたのである。
|
ギ・ボサール氏語録 |
ナントの南東・ランドローという小さな村にドメーヌ・ド・レキュを構えるギ・ボサール氏は、ロワール界隈では予想以上に有名な人であった。これは生産者間での会話に限定せず、ナントのあるレストランのワインリストでも彼のワインはドメーヌ名ではなくて、「ギ・ボサール」表示。念のためにソムリエに「これはドメーヌ・ド・レキュのことか?」と尋ねると、「何を今更、聞いているのだ」という感じである。
ボサール氏が有名である理由の一つに、徹底したビオディナミの実践が挙げられる。しかしSO2添加を極端に控えたワインにありがちな、飲み手によっては抵抗を感じる所謂「ビオ味」が氏のワインには無いように、氏の「ビオ論」も難解さや過激さ(?)よりも、「ブドウ畑にとって必要なことをやっている」という考えが理解しやすく、同時にミュスカデの現状も良く反映しているものでもあった。よってまずは「ギ・ボサール氏語録」(?)を、ここに幾つか紹介したい。
![]() 「ビオ」をなぜ実践するのか?
「ビオ」をなぜ実践するのか?
― ビオディナミを申請・認定されたのは最近だが、私のドメーヌはそもそも30年来のビオロジー。除草剤も化学肥料も昔から使っていなかった。まぁウチが小規模で、加えてここミュスカデは、シャンパーニュやボルドーといった裕福な産地ではなかったから、高い薬剤の普及が遅れた、という事情もあった。
しかし畑仕事が、単に「経済格差」だけで左右されるようでは元も子もない。そもそもブドウとは「痩せた土地で、根が地中深くに必要なものを探しに行くべき」で、私は耕作には馬を使っているが、「観察しながらマジメに耕すこと」と「介入」とは違うもの。つまり麦やキャベツの畑ならともかく、過剰な肥料の投資などは最終的にブドウにとって親切ではない、というシンプルな事実がある。また最近はビオ実践者も増えているが、「ビオを知っていても、ワインを知らない」生産者が多いようにも思われる。
![]() ミュスカデで「100%手摘み」は、珍しいのでは?
ミュスカデで「100%手摘み」は、珍しいのでは?
― 確かに90%が機械摘みのこの地では、私のドメーヌの収穫風景はある意味目立つかも(笑)。そしてもちろん収穫の費用や手間は、機械の方がかからない。
しかし機械収穫にしてしまうと、醸造過程での手間が格段に増す。つまり良くないブドウが混じって、しかも潰れてしまっていてはSO2を添加せざるを得ないし、発酵も自然に始まりにくいので人工酵母も添加しなければならない。また悪い雑味を取り除こうとすると色々細工が必要になり、結果的に良い要素まで取り去ってしまうことになる。「味わいが生まれる大部分が工業的な醸造過程によるもの」というのは、いかがなものか?
![]() 低収量の理由は?
低収量の理由は?
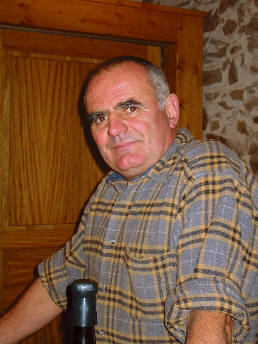 |
| ギ・ボサール氏。「今年のミュスカデは、突出している!」と、2004年の収穫結果に大満足していた。 |
― これも「機械摘み VS 手摘み」と同様で、「高い収量」のブドウほど、醸造では酵母添加などが必要になり、結果的に味わいに影響を与えるのが「醸造過程」に終始してしまう。
要するに以上の言葉から見えてくることを乱暴にまとめると、「畑仕事でラクをすればするほどブドウは本来の性質を失い、醸造で『誤魔化さなければ』ならない」ということだ(それはコント・ラフォンのドミニク・ラフォン氏が「本当に良い魚なら、刺身かシンプルな塩焼きで食べることが出来るだろう?」と言ったことを思い出させた)。また冒頭に書いた、ミュスカデの表現に頻繁に使われる「ピピ・ド・シャ(猫の小便臭)」も、収量の高いブドウを機械的に醸造した時に、この地では欠点として表れやすい味わいなのかもしれない。
ところでしっかりとした酸を持つワインを飲むと、真っ先に思い浮かべるのは「石灰質土壌」。だからドメーヌ・ド・レキュのギ・ボサール氏に「ウチのワインの土壌に、石灰質は全く無い」と言われた時には、ちょっとした驚きであった。ではミュスカデのミネラルを生み出す土壌とは何なのか?そこでボサール氏が提案してくれたのが、「土壌別の飲み比べ」である。
|
テイスティング 〜土壌別にミュスカデを飲んでみる〜 |
このドメーヌの神髄でもある3つのキュヴェ、「Expression de Granite」「Expression de Gneiss」「Expression d’Orthogneiss」。これらを日本語に直訳すると「花崗岩の表現」「片麻岩の表現」「真片麻岩の表現」となる。
ワインの名前に限らず、アルコール類の名前はユニークなものが多いが、これは地質をダイレクトに表記した解りやすいネーミングのようでいて、地質学に疎い者にはピンと来ない。だが氏曰く、「斜面の向き、収穫の時期などに差はあっても、栽培・醸造過程において基本的に同じ作業を施して違う味わいになる。これは土壌から来る要素が大きい」。まずはワインの特色を支える「土壌」を簡単に把握しておきたい(広辞苑やドメーヌの資料から抜粋)。
![]() 花崗岩(Granite、グラニット)
花崗岩(Granite、グラニット)
「深成岩」の一種。ふつう灰白色でこまかい黒い点がある。主成分は、長石・石英・雲母など。固くて美しいので建築・装飾用によく使われる(御影石)。
また「深成岩」とは、地下の深い所でマグマがゆっくりと冷却固結してできた火成岩のこと。完全に結晶していて、構成鉱物の粒が一様に大きい。他にせん緑岩や、はんれい岩など。
ワインには果実味よりもはっきりとしたミネラルを与え、若い時はその酸とミネラルの高さゆえ、非常に「閉じた」印象となり、ミュスカデでも保存状態さえ良ければ10年以上の熟成を遂げるタイプとなる。
![]() 片麻岩(Gneiss、グネス)
片麻岩(Gneiss、グネス)
「変成岩」の一種。花崗岩に似るが結晶化の仕方や構成が異なり、石英・長石などに富む白っぽい部分と、黒雲母などを主とする暗色部分とがしま模様をなすもの。
また「変成岩」とは、水成岩や火成岩など既存の岩石が、地球内部で圧力・温度などの変化や化学的作用を受け、成分・組織を変じてできた岩石(大理石など)。
ドメーヌで見られる片麻岩は結晶成分が少なく、よって「粘土化」しやすい。この性質はワインに果実味・ヴォリュームを与え、最初から「開いた」ワインとなる。
![]() 真片麻岩(Orthogneiss、オルトグネス)
真片麻岩(Orthogneiss、オルトグネス)
「変成岩」の一種だが、片麻岩よりも結晶化が見られ、ワインとしては片麻岩よりも「ミネラル寄り」で、熟成能力も高いワインとなる。
 |
 |
|
Gneiss(片麻岩) |
Orthogneiss(真片麻岩) |
 |
|
|
Granite(花崗岩) |
つまりミュスカデは「花崗岩と、その仲間的な土壌」に支えられて生まれるワインであり、イメージ的には「キラキラした結晶成分の多い土壌になればなるほど、よりミネラリーで長命なワインとなる」。またドメーヌではミュスカデの魅力の一つが「果実味とミネラルのバランス」であることを尊重して、ブドウは酸を残した状態の時に収穫され(過熟は望まれない)、収穫時期の「早い・遅い」と飲み頃の「早い・遅い」も一致するらしい。
実際にテイスティングしても3つのキュヴェの味わいはハッキリと異なり、私たち訪問者が先入観無しに述べたコメントも「果実寄りで開き、すぐに飲みたいミュスカデ」「ミネラル寄りで閉じ、時を待ちたいミュスカデ」「その中間」は、それぞれ「片麻岩」「花崗岩」「真片麻岩」に相当した。そして後日見た各ワイン本の味のコメントとも見事に一致を見、つまりこれは、誰にとっても同じように「違いが感じられる」と言っても良いのではないだろうか。
しかしこの日の試飲で最も印象深かったのは、「Expression de Granite(花崗岩の表現) 1999」であった。「このボトルを開けたら、1999年はウチにマグナムしか残らない」と苦笑しつつ提供してくださったそのワインには、焼き栗やアーモンド、ノワゼット様のナッティさ、アプリコットやパイナップルなど黄色くて酸と甘味も豊かな果実、ポワローなどの香りが複雑に混じり合い、心地良い苦みを残しながら酸とミネラルが余韻を長く引っぱっていく様子には、確かに「まだ数年は余裕で楽しめそう」なポテンシャルに溢れている。
「丁寧に造られたミュスカデは、土壌によっては熟成させた方がより楽しめる」ことを、このドメーヌの「花崗岩の表現」は見事に舌に訴えてくるのだ。
ミュスカデ。ともあれ軽視されがちで、キリキリに冷やして何も考えずに喉に流し込むのも、それはそれで楽しいワインではある。だが生産者を選べばとてもリーズナブルに、様々な味わいを一杯のグラスで楽しむことが出来、それらの味わいは日本の食卓とも併せやすいものであると思う。
ドメーヌを出た4時過ぎ、既に日は傾きかけ、寒さも忍び込んできていた。しかしこの寒さもボサール氏のミュスカデを飲んだ後には、「海鮮鍋とポン酢、それを『真片麻岩』で飲るのもイイかな」などという、楽しい想像に変わっていることに自分でも驚きつつ、次の訪問先に向かったのであった。